退職が近付く50代必見!!確定拠出年金の上手な受け取り方
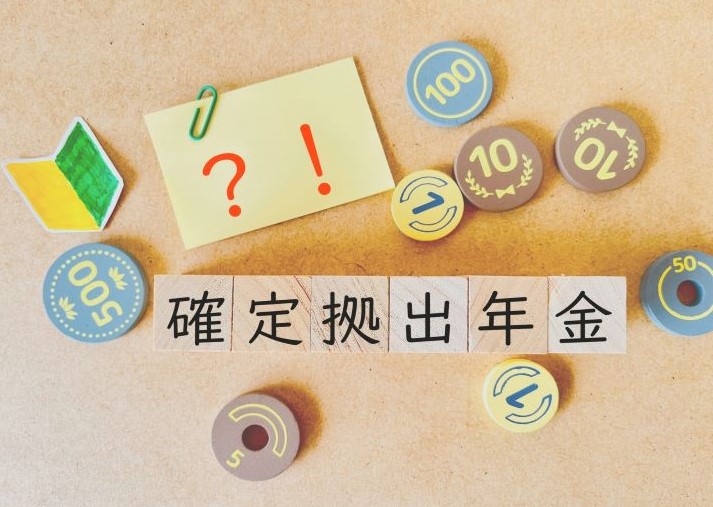
確定拠出年金は、年金もしくは一時金のどちらで受け取るかによって、税制上適用される控除も異なるため、手取り金額に大きな差が出てしまう可能性があります。
そのため、事前に受け取り方を想定しておくことは重要といえます。
本稿では、2種類の受け取り方の違いについてご説明するとともに、受け取りに向けて今から取り組むべきことを解説いたします。
受け取り方の違いと税制上の取り扱い
確定拠出年金の受け取り方には、「年金として受け取る」「一時金として受け取る」という方法があり、両者を併用することもできます。
「年金受け取り」の場合
雑所得として扱われ、公的年金(国民年金・厚生年金など)と合算した収入金額から「公的年金等控除額」を差し引いた残額が所得となります。
雑所得は、他の所得(給与所得・不動産所得など)と合算して税額を計算します(総合課税)。
そのため、年金受け取りを選ぶ際には、年金以外の収入との兼ね合いによっては課税される所得額が増え、さらにその結果として健康保険料の支払いが増えたり、医療費の自己負担割合が高くなったりする可能性があることを考慮する必要があります。
「一時金受け取り」の場合
退職所得として扱われ、企業から受け取る退職金等と合算した収入金額から「退職所得控除額」を差し引いた残額の2分の1※が所得となります。
さらに、退職所得は、他の所得と合算せずに単独で税額を計算しますので、税負担が軽減される仕組みになっています(分離課税)。
退職所得控除は、勤続年数が長いほど金額が大きくなるため、退職一時金と合算した金額が退職所得控除の範囲内であれば全額非課税で受け取ることもできます。
※「特定役員退職手当等」「短期退職手当等」は計算式が異なります。
年金と一時金それぞれの所得計算方法
確定拠出年金のメリットとして、受け取り時の控除があります。所得の計算方法は以下になります。
年金受け取りの場合
公的年金等に係る雑所得の計算方法
「公的年金等に係る雑所得の金額=公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」
上記の収入金額は、公的年金も合算した金額であるため、いくら公的年金が受け取れるのかも確認しておく必要があります。50歳以上の「ねんきん定期便」では、65歳以降に受け取る年金のおおまかな金額を確認することができます。
雑所得は、年齢やその他の所得・年金収入の金額によって計算方法は異なり、以下の【図表1】の公的年金等控除額を使って算出します。
図表1:公的年金等控除額の速算表(令和2年分以後)
| 受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額 (A) | 公的年金等控除額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円未満 | 60万円 |
| 130万円以上~410万円未満 | (A)×25%+27.5万円 | |
| 410万円以上~770万円未満 | (A)×15%+68.5万円 | |
| 770万円以上~1,000万円未満 | (A)×5%+145.5万円 | |
| 1,000万円以上 | 195.5万円 | 65歳以上 | 330万円未満 | 110万円 |
| 330万円以上~410万円未満 | (A)×25%+27.5万円 | |
| 410万円以上~770万円未満 | (A)×15%+68.5万円 | |
| 770万円以上~1,000万円未満 | (A)×5%+145.5万円 | |
| 1,000万円以上 | 195.5万円 |
注)「公的年金等に係る雑所得」以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の方
一時金受け取りの場合
退職所得の計算方法※
「退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2」
※ 「特定役員退職手当等」「短期退職手当等」は計算式が異なります。
収入金額に合算される企業の退職一時金は、会社の人事などの担当部署や社内のイントラネットなどで確認することができます。
退職所得控除額は、勤続年数が長くなれば大きくなり、【図表2】のように計算します。
図表2:退職所得控除額の計算表
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
注)勤続年数の端数は切り上げ
以上のような控除を最大限活用し、受け取り方を工夫するだけでも手取り金額をできる限り減らさず受け取ることが可能です。
税制メリットを活かす受け取り方は?
企業の退職金も合わせた一時金が、退職所得控除額を超えてしまう場合、超えた金額を年金受け取りにすることで、全額を非課税にすることも可能です。
たとえば、勤続年数38年の方が60歳で退職する場合、退職所得控除の2,060万円(※)の範囲内で一時金を受け取れば非課税となります。
※ 退職所得控除2,060万円=800万円+70万円×(38年-20年)
もし、全額を一時金で受け取った場合、退職所得控除額を超えてしまう方は、超えた金額を年金で受け取ることで公的年金等控除を活用することも可能です。
仮に、年金収入を65歳未満は年間108万円以内(※1)、65歳以上は158万円以内(※1)におさえると、所得税が非課税になります(※2)。
※1 所得税の基礎控除額48万円を公的年金等控除額に加えた金額(住民税は、基礎控除額43万円を公的年金等控除額に加えた金額以内であれば非課税)
※2 年金収入以外に収入が無い場合
もっとも2023年6月に政府が発表した「経済財政運営と改革の基本方針2023」(骨太の方針)の中で「退職所得課税制度の見直しを行う」ことが明記されており、一つの会社で長く働く人ほど税負担が軽減される現在の仕組みが改められる方向で議論が進んでいますので、今後の動向にも注意が必要です。
一時金の控除が縮小される見直しが行われた場合は、年金受け取りを併用する方法がより重要になってくると思われます。
老後の収支を確認したうえで受け取り方を決めましょう
ここまでは、税制上の控除を中心に受け取り方法をお話してきましたが、確定拠出年金の受け取り方を決める際には、老後の資産が枯渇しないようにすることも重要です。退職所得控除があるので一時金で全額受け取ったものの、お金があるからと言って旅行や車等に散財してしまっては後悔することになります。
「老後は生活費やリフォーム費用などどのくらいの支出が必要か」「公的年金その他でいくらの収入が見込めるのか」といった点を把握し、それを踏まえて受け取り方を決め、計画的に支出していくとよいでしょう。
また、受け取り方を決める以前に、確定拠出年金の原資を大きく減らしてしまい、想定していた通りの老後の生活が送れないことになっては困ります。
そうならないためにも、今一度、確定拠出年金の運用配分を確認し、もし株式の比率が高い場合は、受け取り時期が近付くにしたがって徐々に債券の割合を増やし、運用資産全体のリスクを落としていくことなども検討すべきです。
まとめ
確定拠出年金に加入されている50代の方は、お勤め先の退職金や公的年金の受け取り見込額を確認した上で、「自分は年金受け取り、一時金受け取りのどちらでいくら受け取ると税制上メリットがあるのか」を一度みていただくことをお勧めします。
そして退職時に受け取り方を決める際には、税制上のメリットを十分踏まえながらも、その時点の金融資産や老後のライフプラン、収支見込みなど様々な点を考慮して決めていただくのがよいでしょう。
ご留意事項
本稿は、如何なる意味におきましても、将来の成果を示唆または保証するものではございません。最終決定は、ご自身の判断で行ってください。
記載内容等については、2023年7月現在の情報に基づいて作成しております。今後、事前の連絡なしに変更される場合があります。
また、本稿の一切の権利はオンアドに属しております。事前にオンアドの承諾を得ることなく、複製・転載・転送等の行為は固くお断りいたします。



